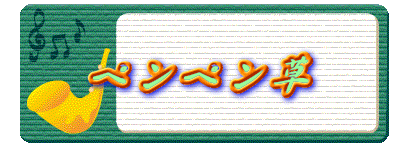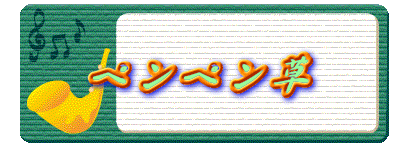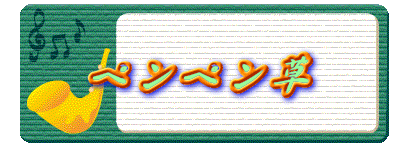第34段 * 神聖ローマ帝国 その成り立ち Part4 * フリードリッヒⅡ世 *
1197年9月皇帝ハインリッヒ六世がシチリアで32歳の若さで急死、幼い3歳のフリードリッヒが残された。母コンスタンツァは前皇帝の遺言でシチリア王国の摂政となる。3歳のフリードリッヒと摂政のコンスタンツァ二人では帝国とイタリアへの睨みが利くはずがない。たちまちドイツとイタリア間のフリードリッヒ争奪戦が起きる。”幼き天子”フリードリッヒは苦難の道を歩むことになる。
前皇帝の弟シュヴァーベン公フィリップがフリードリッヒをドイツ王とし、自らは後見人としてイタリアへやって来る。一方シチリアではシュタウフェン家のミニステリアーレス上がりのラヴェンナ公マウクヴァルトが、シチリア支配の為の傀儡としてフリードリッヒを我が手にと目論む。摂政コンスタンツァはどちらも我が子には有害で信用できない存在と見做した。だとするとローマ教皇インノケンティウスⅢ世に仲介を頼むしかない。結局母はシュヴァーベン公がドイツ王に就くことを承認し、代わりに我が子フリードリッヒがシチリア王に就くことを認めさせた。1198年5月4歳のフリードリッヒはシチリア王として戴冠を受けるが、その時教皇のシチリア宗主権を認めた。”シチリアの宗主権を認める”なんてとてつもない妥協であるが、母子の当時置かれている状況下ではやむを得ぬ選択であろう。同年11月母は”教皇インノケンティウスⅢ世を息子の摂政とする”と遺言を残しこの世を去った。
こうなればフリードリッヒは教皇インノケンティウスⅢ世の掌中にあり思うがままになるはず・・・であった。帝国とシチリア王国が同一の王となり挟撃される危機は免れた。そして幼き王を教皇の言うことを素直に聞く従順な下僕にすれば良い。教皇はシチリア王国の首都パレルモに配下の中から優秀な人材を家庭教師として送り込んだ。とここまでは予定通りだったが、そのまますんなり問屋が卸したのでは世の中つまらない。このフリードリッヒは6ヶ国語を自在に操るほど語学は堪能、更に知力、体力にも優れた「早熟の天才」だったのである。これは教皇にとってとんだ見込み違いであった。
シチリアは少し前まではイスラム国家の支配下にあった。地域の特殊性もあり、ここはイスラム文化、ビザンツ文化、ラテン文化にキリスト教文化が入り組み共存する地域である。パレルモはその中心に位置し、そこでフリードリッヒはヨーロッパとオリエントの文化に接することができた。このことが彼の中に多様な価値観を醸成した。
1209年フリードリッヒが14歳に成長すると、教皇インノケンティウスⅢ世は摂政のお役御免となる。その前年ドイツ王がフィリップが暗殺されて空位になっている。ここでフリードリッヒにドイツ王を継承されては以前と同じ状況が復活してしまう。そこでこれを阻む為に教皇は奇策をとる。1209年フィリップの対立王オットー・・・ハインリッヒ獅子公の嫡男・・・を皇帝として承認、即ちオットーⅣ世を強引に皇帝に推挙したのである。この”教皇によるドイツ王選挙への介入”は後々先例となり大きな影響をもたらすことになる。教皇は「諸侯により選ばれた王を皇帝に就けるのが教皇の責務」と宣言した。オットーⅣ世はシュタウフェン家の宿敵ヴェルフェン家の出である。シュタウフェン家が認めるわけはなく、両家の対立が再燃しドイツは大混乱に陥る。
ところがオットーⅣ世はこともあろうに恩人の教皇を裏切りシチリア王国を侵略する。これには教皇も怒り心頭で、オットーⅣ世を破門する。諸侯はこれを受けてオットーⅣ世の廃位とフリードリッヒの皇帝推挙を決定した。教皇はフリードリッヒの皇帝就任前に更なる手を打つ。「ローマ教皇庁のシチリア王国の宗主権の更新」と「シチリア国王を生まれたばかりの長男ハインリッヒへの譲位」をフリードリッヒに認めさせたのである。
神に仕えるローマ教皇や聖職者は本来”清く、正しく、美しく”を実践し全ての国民の手本とならなければならない。ところがここまでいろいろと書いてきた様に、彼らの多くは世俗権力に執着し領土の拡張や金儲けに奔走する有様である。欲の権化と化したかの如きローマ教皇、聖職者達と皇帝、諸侯ら世俗権力との間で衝突が起こり当然世の中は乱れる。これでは救われない。だからこそ歯止めをかけるべく後の「宗教改革」の様な世直し運動が起きて正しい方向へ戻そうとする動きが出てくる。
後世になりモーツァルトとザルツブルクの大司教の確執で、モーツァルトが大司教に反抗し叩き出される。以前は大司教は神に奉仕する神官であるのに何故あれほど権力と財力を持ち傍若無人に振舞っているのかわからなかった。それがようやくわかってきた。この大司教はザルツブルク教会領のお殿様、つまり世俗権力者の諸侯と同列、いや世俗諸侯そのものに他ならない。おまけに聖職者の権威と世俗諸侯の権力を併せ持っているのだから余計始末が悪いのだ。
1212年フリードリッヒは教皇の出した条件を全て認めた様なフリをしてドイツに進撃、オットーⅣ世を打ち破る。1215年20歳のドイツ王フリードリッヒⅡ世が誕生した。戴冠式の際フリードリッヒⅡ世は十字軍遠征を教皇に約束する。教皇は彼の長男ハインリッヒのドイツ行きを認めた。1216年教皇は思うとおりになったと確信、満足したままこの世を去る。
1220年フリードリッヒⅡ世は皇帝位に就き、息子のシチリア王ハインリッヒを共同統治者としてドイツ王とした。以前のローマ教皇庁との約束を破棄したのだ。皇帝はドイツ統治を息子に任せ、自身は無政府状態のシチリア王国の再建に取り組む。これには教皇ホノリウスⅢ世は大いに怒り皇帝の破門を匂わせる。皇帝は取り合えず教皇に十字軍遠征を約束しその場を凌いだ。しかしながら皇帝は約束を実行しようとはせず、そんな中教皇は死去する。次のローマ教皇グレゴリウスⅨ世は即座に伝家の宝刀”破門”をちらつかせる。止むを得ず皇帝は十字軍遠征に出向くが、途中皇帝は病気になりパレスチナまで行かずに帰還する。怒り心頭の教皇は20日後皇帝を破門した。
皇帝は息子ハインリッヒをドイツ王実現の為に、ドイツの大司教、司教などの聖職者との妥協を図った。1220年「聖界諸侯との協約」を結ぶ。これにて聖職者の教会領の支配権限を認め、彼らを”諸侯”に列したのである。次に1231年(世俗)諸侯と「諸侯の利益の為の協定」を結び、彼らの大幅な特権を認めた。これによりドイツには数多くの国家ができあがる。ドイツが長年に亘り分裂国家となり統一国家形成が遅れた源はここにあると言っても良い。皇帝の帝国統治の基盤はイタリアであり、イタリア以外は古代「ローマ帝国」同様属州である。皇帝は治世の大半をイタリアですごした。するとドイツは統治者不在と言うことになる。統治者不在と言うことになれば、属州には帝国からの分離独立の動きが起きやすい。そこで属州同士で足を引っ張り合う状態にしておけば、統治者不在でも分離独立の動きを牽制できると言う理屈なのだ。
1228年6月破門の身ながら皇帝は第6次十字軍遠征に出向く。アラビア文化に精通しアラビア人とも深く交わる皇帝は,イスラム世界との争いを嫌いアイユーブ王朝のスルタンのマリア・アル・カ-ミルと交渉を重ねる。両者はヤッファ条約を結ぶ。エルサレム・ベツレヘム・ナザレの3都市をキリスト教側に返還するが,エルサレムはキリスト教、イスラム教2つの宗教の共同統治下に置かれることになった。皇帝はエルサレム城でエルサレム王の戴冠式を執り行なう。前にも書いたが皇帝は多様な価値観を持っている。自分の王国をキリスト教一色にしようとは考えず、異教徒の共存を許したのである。広大な領域をキリスト教のみで統治することには無理があることを承知していた。政治的には統一したが宗教的には共存を認める柔軟性により「世界帝国」と成り得た古代「ローマ帝国」を皇帝は理想とした。理想実現の為には教皇の言う”神権政治的”国家秩序を排除しなければならない。とすれば皇帝と教皇の全面対決は当然の成り行きである。
ドイツ王ハインリッヒはいつまでも単なるドイツ総督にすぎないことに不満に思っていた。むろん皇帝の政策「諸侯の利益の為の協定」が原因である。ハインリッヒは国王としてドイツを統治したい。しかし諸侯は協定を楯にハインリッヒに強く迫ってくる。父を憎む息子に教皇の魔の手が伸びる。バルバロッサをコケにしたロンバルディア都市同盟との連携を盛んに勧める。ついにハインリッヒは教皇の挑発に乗り、1234年父に対して反乱を起こす。彼の所には諸侯は全く味方せず、集まるのはミニステリアーレスのみ。ロンバルディア都市同盟は防衛戦では強力だが侵略戦では威力を発揮できない。これでは勝負にならず息子の反乱はあっさり鎮圧される。息子は父により目をつぶされ監禁され、数年後に別の場所に移動中に谷底に身を投げて一生を終えた。
皇帝は嘆いてばかりもおられず、反乱鎮圧後次男コンラートをドイツ王とする。更にロンバルディア都市同盟を完膚なきまでに叩き潰す。これに対して教皇グレゴリウスⅨ世はいったん取り消した破門を再び宣告する。今度は皇帝も反撃し、教皇主催の会議に参加しようとする枢機卿などの聖職者を逮捕した。これには教皇もどうすることができず1241年死去する。
次の教皇は僅か在位17日で死去、1年半の空白の後にその次の教皇としてインノケンティウスⅣ世が選出された。教皇は皇帝を嫌いフラスのリヨンに逃亡する。しかしこの教皇は一見弱気に見えるが、なかなかしたたかで手強かった。教皇はリヨンで皇帝フリードリッヒⅡ世の破門を宣言するが、皇帝はこれを無視する。すると次は教皇は「皇帝任命権は教皇の絶対権限」と宣言し、皇帝に対する十字軍を諸侯に呼びかける。これだけ矢つぎばやに攻められるとさすがの皇帝も追い詰められる。諸侯も何だかんだ言っても結局はキリスト教徒であり教皇が怖い。ドイツ、イタリアで諸侯の反乱が相次いで起きると、皇帝は直属のイスラム教徒の部隊を率いて応戦した。次男のドイツ王コンラートⅣ世には対立王が立てられる。シュタウフェン家の状況が悪化する中で、1250年12月皇帝フリードリッヒⅡ世はこの世を去る。
ここに事実上シュタウフェン家は崩壊する。皇帝の死後息子や孫達は18年間戦い続ける。しかしながら1268年に孫のコンラディンがナポリで処刑され、そして1272年に末子エンツォがボローニャで獄死する。これでシュタウフェン家は断絶した。
この後”皇帝のいない時代”、いわゆる「大空位時代」が生じる。対立王は存在するが皇帝として戴冠を受けた王が23年間誰一人としていない。その「大空位時代」にはじめて『神聖ローマ帝国』の名称が登場する。そんな時代を経て「ハプスブルク」家の皇帝ルドルフⅠ世が登場する。そのあたりの事情は次章で触れることにする。