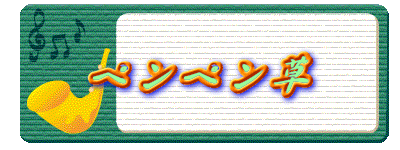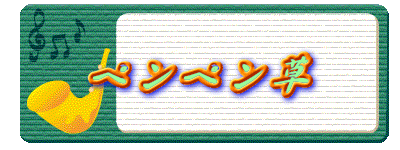第73段 * 堀江氏の野望 その6 − 今回の問題の原点は何か? − *
800億円、3000億円などと一般庶民には縁遠い金額が飛び出して来ては、フジテレビvsライブドアの闘いはもはや「マネーゲーム」化している観は否めない。ごく一部のステークホルダー(利益関係者)が他のステークホルダーの意思とは無関係に自らの利益の為だけに動いている様に見えてしまう。 ところで今回の問題が何故起きたのか原点に立ち戻り改めて状況を眺めてみたい。
最大のポイントはフジサンケイグループの歪んだ資本構造にある。フジサンケイグループの中核企業はフジテレビだが、資産価値、売上高などの企業価値がはるかに低いニッポン放送がフジテレビ株式の22.5%を保有する筆頭株主になっている。フジテレビはサンケイ新聞社、扶桑社、ポニーキャニオンなどの大株主という関係にある。つまりニッポン放送株式を取得して経営に対する影響力を強めれば、同時にフジテレビの経営に対して影響力を持つことができることは誰が見ても明らか。ライブドアが”本丸”フジテレビではなく、”出城”のニッポン放送に狙いをつけたのは当然と言うべきだろう。歪んだ資本構造を長年放置して隙を突かれた形になったフジサンケイグループ経営陣の怠慢が今回の事態を招いたと言える。
ニッポン放送とフジテレビの不自然な関係を是正しようとようやく動き出した矢先、ライブドアの”暁の急襲”を受けて一挙に苦しい立場に追い込まれている。先に不自然な関係に目をつけたのは堀江氏ではなく、M&Aコンサルティング(村上ファンド)の村上代表なのだ。1999年通産官僚を辞めて投資顧問会社を設立しその手腕を発揮して行く。ニッポン放送株式を約18%取得した村上氏は、2004年6月の株主総会で「持ち株会社の設立」を主張した。村上氏は何度か発言を繰り返していたが、突然ニッポン放送亀淵社長が討議を打ち切り議題の採決を行ない株主総会を閉会した。
村上氏はファンドの代表として利益を追求する一方、”モノを言う株主”として企業の問題/課題の提起と改善策の提案を行なっている。ニッポン放送の株主として「フジサンケイグループの歪んだ資本構造改善」を目指して「持ち株会社の設立」を提案した。しかしながらニッポン放送側は村上氏の発言を遮り、かつ討議中止と言う侮辱的な対応で無視してしまった。この時村上氏は怒り心頭で「この様な会社はいずれ買収される」と述べたと言われる。村上氏の遺恨は相当なものと推察される。もしかしたらこの時「ニッポン放送の現経営陣では何も変わらない。総入れ替えしなければダメ。」と村上氏は心に決めたかもしれない。
当初村上氏は現経営陣の降板までは考えておらず、むしろ問題改善に協力しようとする姿勢だったと思われる。それに侮辱的対応で応じてしまったのが今回の騒動に繋がっている可能性がある。大株主とは言っても村上氏は1/5程度で、現経営陣はあなどっていたのではないか?多くの協力的な株主が支えてくれるので安泰だと考えていたのだろう。ニッポン放送をはじめフジサンケイグループ経営陣は「この時話に応じていれば・・・」と後悔しているかもしれない。経営者として先見の明がなかったと非難されても仕方がない。
村上ファンドとライブドアは同じビル(六本木ヒルズ)にあり、村上氏と堀江氏は親交があり意見交換も行なっている。フジサンケイグループについても相当突っ込んだ議論をしていた可能性がある。ニッポン放送経営陣に”三行り半”を突きつけた村上氏は、堀江氏に様々な助言をしていることも考えられる。フジテレビがニッポン放送のTOBを実施したタイミングを見計らって堀江氏が行動を起こしたとも見られ、半年かけてじっくり練られた用意周到な戦略に沿い闘いを仕掛けていると言える。その攻勢に対して無防備にノホホンとしていたフジサンケイグループは屋台骨を揺るがされて動揺を隠せない。フジサンケイグループの苦し紛れの対応が如実に示している。
フジサンケイグループには事実上の創業者とも言える鹿内(シカナイ)家による支配と同家との闘いが大きな影を落としている。この因縁めいた歴史が間接的に今回の騒動に繋がったとの見方もできる。そのあたりをもう少し詳しく触れることにする。
フジサンケイグループの創設は今から50年前1954年のニッポン放送開局時に遡る。この時鹿内信隆氏は日経連専務理事から専務として経営に参画した。信隆氏はニッポン放送株式取得を続けついには実権を握る。信隆氏にとり最初にマスコミ産業に関わったのがニッポン放送であり、同社がグループの親会社の位置付けになったと見られる。1957年文化放送と共にフジテレビを設立し1967年には社長に就任する。同じ頃財界の要請を受けて、経営危機に直面した産経新聞社を再建している。この様にして信隆氏はテレビ、ラジオ、新聞の三大メディアを保有する体制を確立し、初代フジサンケイグループ議長に就任した。
1985年長男春雄氏が二代目議長に就任して鹿内家による世襲が順調に踏襲されると思われた。ところが1988年春雄氏が何と42歳の若さでこの世を去る。鹿内家にとってはまさに青天の霹靂、信隆氏は急遽娘婿の宏明氏を議長代行として自らは“後見人”として議長に復帰した。1989年宏明氏は議長に就任したが、その経営手腕を巡りグループ内で強い不満が湧き上がる。
1990年信隆氏が亡くなるとグループ内の状況は一層不安定になり、1992年宏明氏は産経新聞社取締役会で突如会長職を解任される。解任理由は「マスコミ人としては相応しくない。企業の私物化は許されない。」とはなっているが、理由なんぞどうでもよく適当にでっち上げたのでないか?翌日宏明氏はグループ議長、フジテレビ会長、ニッポン放送会長を辞めさせられ、フジサンケイグループから追放された。このクーデターの黒幕は当時のフジテレビ日枝社長(現会長)で、就任したばかりの産経新聞羽佐間社長を動かして解任劇を成功させた。
但し宏明氏はグループから追放はされたが、依然としてニッポン放送株式の51%保有していた。これは日枝氏にとっては大変な脅威であり、もし宏明氏がニッポン放送内で力を取り戻せば再びグループの中枢に返り咲く可能性がある。宏明氏の影響力を排除する為には、ニッポン放送、フジテレビを上場する必要がある。上場による第三者割当増資を行なえば、宏明氏のニッポン放送、フジテレビの持ち株保有比率を下げることができ結果として宏明氏の影響力を排除できる。1996年ニッポン放送、引き続き1997年にはフジテレビが上場を果たし当初の狙いを達成した。2005年初めに鹿内家の保有株式が全て大和証券SMBCに売却され、フジサンケイグループへの影響力が完全に排除された。
フジサンケイグループがニッポン放送、フジテレビの上場により鹿内家の影響力排除に成功したまでは良かったのだが、ここで安心してしまいフジサンケイグループの歪んだ資本構造の改善を怠った。この時ニッポン放送とフジテレビの不自然な親子関係を改善しておけば、今回の様な騒動が起きることはなかった。2005年6月株主総会での村上氏の提案も含めて、フジサンケイグループは2度も改善のチャンスを逃している。経営者として失格の誹りを免れない。
ある経済評論家は「30%以上の株がライブドアに売られたことが、経営者に対する株主の不信任」と述べている。フジサンケイグループの過去からの一連の行為が、一般株主の不信感を徐々に増幅させ今回一挙に爆発させたと思われる。口先だけで「株主の利益を優先」などと言ってもすぐに正体がばれる。企業の経営者は株主をはじめ全てのステークホルダーを大切にしなければならない。
フジサンケイグループが鹿内家との抗争に勝利して安心しきっていたが、隙を突かれて外資や村上ファンドに足元を掬われる格好になった。経営者としては失格と言ってもよい。”上場”と言う手段で鹿内家を排除したフジサンケイグループが、逆に”上場”を利用して買収攻勢を浴びるとは何とも皮肉な話・・・”身から出た錆”とでも言うべきか?
堀江氏の今回の行為はぬるま湯にどっぷり漬かっている日本経済界に警鐘を鳴らしたことは一定の評価はできる。フジサンケイグループの経営陣は”聞く耳持たず”で、潜在する危機を解消する努力を怠たった。戦国時代の風雲児織田信長の如く巧みな戦法を駆使して旧体制に挑戦している。日本経済界を震撼とさせている今回の行為は決して新しい手法ではなく、1980年代にアメリカでは敵対的買収の嵐が吹き荒れた。その後対策も確立され、現在ではすっかり影を潜めている。ところが日本経済界は”日本はアメリカとは違う”とあくまでも「他山の石」と決め込んでいた。そこへ堀江氏が大きな風穴を開けたので、日本経済界(日本政府も含めて)は否応なしに改革を迫られたと言える。
しかしながらライブドアの今回の手法、考え方には疑問点が多く存在する。容認できない部分も多々ある。それはさておいて上場企業であればいつ何時買収攻勢に晒されるか分からない。経営陣は今回の騒動を「他山の石」とはせずに常に危機感を持ちリスク管理しなければならない。従来の安定株主による”株式の持合い”による”事なかれ主義”は通用しなくなってきている。法改正や企業のリスク管理対策の徹底で今回の様な手法は通用しにくくなるかもしれない。しかしながら必ずどこかに抜け穴はあるもので、”賢い”人間はそれを見事に探り当てる。企業の経営者は常にアンテナを張り巡らせ注意を怠ってはいけない。それに加えてステークホルダー全てを大切にしないと、どこかで綻びが生じ企業経営が破綻することもあり得る。今回のフジテレビvsライブドアの闘いはいろいろな意味で多くの教訓を残している。更に新たな教訓がまだこれからも出てくるだろう。