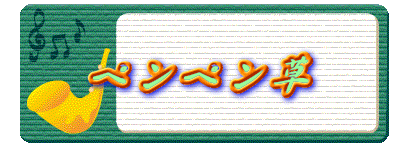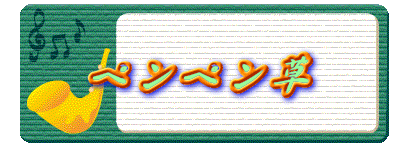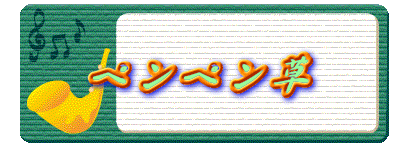第35段
* 神聖ローマ帝国 その成り立ち Part5 * 大空位時代、そして神聖ローマ帝国の出現 *
「大空位時代」はフリードリッヒⅡ世がこの世を去った1250年からハプスブルク家のルドルフⅠ世がドイツ王となる1273年迄とされる。「大空位時代」には1国に2人の王が対立していた。しかしながらいずれのドイツ王もローマ教皇から皇帝戴冠を受けることはなかった。と言うことはこの時代には皇帝不在である。それに加えてどの王も”皇帝の威厳”なんぞ誰も持ち合わせていなかった。皇帝の権力が空洞化し諸侯の権力が増大していることを象徴的に示している。この状況は日本で言えば南北朝時代に南朝、北朝が各々天皇を擁立し争った時によく似ている。
王位を巡る状況はめまぐるしく変化していく。皇帝フリードリッヒⅡ世が教皇インノケンティウスⅣ世に破門・廃位された時、チューリンゲン地方伯ラスペが対立王として起つ。チューリンゲン地方伯が死去すると、1247年ホラント伯ウィレムがが対立王として起つ。皇帝がこの世を去ると次男コンラートⅣ世に対立する。1254年コンラートⅣ世がこの世を去り、2年間だけウィレムが単独王となる。ウィレムが死去すると、1257年スペインのカスティリア王アルフォンソⅩ世とイギリスのコーンフォール伯リチャードの2人が「ドイツ王」を名乗る。2人共にドイツ諸侯ではない外国人である。どさくさまぎれに特権や領地を狙っている諸侯にとっては、2人共傀儡王として申し分なかったのである。アルフォンソⅩ世はやがて息子サンチョⅣ世にカスティリア王の座を奪われるという醜態を晒す。ここまで実体の無い王ばかりではどうにも救いようがない。”王権”も地に墜ちたものである。
これらの「ドイツ王」の内、ホラント伯ウィレムはまだましな方である。1254年コンラートⅣ世がリヨンの教皇インノケンティウスⅣ世に臣下の礼をとり一応「ドイツ王」として認めてもらう。しかしながら皇帝戴冠を受けることはなかった。コンラートⅣ世がこの世を去ると、単独王のウィレムに諸侯は色目を使う様になる。とは言ってもウィレムの”王権”は皆無に等しい。
ウィレムは何とかして”見かけだけ”の国王(=ドイツ王)から抜け出そうとして努力する。実体の無さを外見で補おうとする。外見を整えれば実体がついてくると考えたのだ。1254年彼は公文書に『神聖ローマ帝国』の名称を使用する。コーンフォール伯リチャードも『神聖ローマ帝国』の名称を使用する。外見は整えたのだが実体を整えることは彼には到底不可能、1256年冬フリースラントへの遠征中に人知れず落命した。経緯はどうあれ、これで『神聖ローマ帝国』が”出現”したのである。
1272年コーンフォール伯リチャードが死去すると、業を煮やしたローマ教皇グレゴリウスⅩ世は諸侯に対し「新国王の速やかな選出」と「選出できない場合は教皇自ら新国王の選定」を通告した。教皇も帝国の騒乱にはだいぶ被害を受けていた。それにこの機に乗じてフランス国王フィリップⅢ世が皇帝候補に名乗りを上げる。フランスはドイツ乗っ取りを狙ったとも言える。フランスにドイツが加わった強大な帝国ができたら、それこそローマ教皇の権威なんぞどこかへ吹き飛ばされてしまう。教皇はそんなことになったらたまらない。
教皇の通告を受けて諸侯が重い腰を上げる。と言っても全ての諸侯に国王選挙権があったわけではなく、この当時は有力諸侯7人(=選帝侯)により国王が選ばれるシステムであった。選考過程ではまずチューリンゲン泊フリードリッヒ、次いでライン宮中伯ルードヴィッヒが候補として名前が挙がるが、いずれも何らかの問題を抱えていてとても国王には選ぶことができない。そこで選帝侯のマインツ大司教とニュルンベルク城伯(実際に選挙権を持つのはライン宮中伯)が、諸侯にとって都合の良い(扱いやすい)候補者として「ハプスブルク」家のルドルフ・フォン・ハプスブルクを推薦した。結局選帝侯会議は新国王としてルドルフを推挙することになる。『神聖ローマ帝国』皇帝ルドルフⅠ世の誕生である。諸侯の中でも弱小貴族で人畜無害と見做されたが故に選ばれたのだが、皮肉にもこれが将来”ハプスブルク家が皇帝位を長期に亘り独占する礎”になった。実はもう一つ皮肉な話がある。ルドルフⅠ世の皇帝就位、ハプスブルク王朝の創設に尽力したニュルンベルク城伯ハインリッヒはホーエンツォレルン家の当主である。後年このホーエンツォレルン家がプロイセン王国を興し、1866年オーストリアを完璧に打ち破りハプスブルク家をドイツから叩き出すことになる。まさに”歴史の妙”だ。
国王ルドルフⅠ世については、第20段[* ハププスブルク家 その成り立ち * その誕生 *]で詳しく述べているのでそちらを参照されたい。
ルドルフⅠ世は選帝侯はじめ諸侯はルドルフⅠ世が思ったよりもはるかに”優れもの”でかつ”したたか”なのには大いに困惑した。彼らは絶対的な王権による強大な国家ではなく、逆に王権を制限し自らの権勢を強く主張できる連邦国家があるべき姿なのである。そこで彼らはオットーⅠ世以来続いている「世襲選挙王制」から”世襲”を取り除き「選挙王制」にしたのである。1291年7月ルドルフⅠ世がこの世を去ると、彼らはハプスブルク家から王位を召し上げナッサウ家のアドルフを新国王に推挙した。ところが1298年アドルフはあっけなくこの世を去る。選帝侯達の努力は水泡に帰すのである。
紆余曲折の後1298年再び王位はハプスブルク家に戻ることになる。ルドルフⅠ世の長男アルプレヒトⅠ世がドイツ王に選ばれた。彼はその卓越した政治的手腕や指導力などから、既に諸侯からは警戒の目で見られていた。才能溢れる国王アルプレヒトⅠ世の手でハプスブルク家の世襲、繁栄が成るかと思われた。ところでハプスブルク家はもともとスイスの出身で後にオーストリアに本拠を移している。スイスは代官が支配していた。スイス領内ではハプスブルク城に近い3つの州(シュヴァーツ、ウンターヴァルデン、ウーリ)が誓約同盟を結び、反ハプスブルクの意志で一致してアルプレヒトⅠ世に激しく抵抗していた。あの有名なシラーの戯曲『ウィリアム・テル』に出てくる悪代官ゲスラーの上司、スイスを抑圧する悪王として登場するのがアルプレヒトⅠ世である。アルプレヒトⅠ世はハプスブルク家の権勢拡大への意気込みが強すぎて他者のことへの配慮が足りないという欠点があったと言われている。そのことが原因となったのか、1308年5月アルプレヒトⅠ世は甥のヨーハンとその一味に暗殺される。
一方「大空位時代」にドイツが大混乱に陥っている最中にイタリア情勢は激変していた。シチリア王国はフランスのアンジュー家の手に墜ち、またローマ教皇庁はフランス王家の掌中に握られている。ドイツ王が皇帝としてローマ教皇を保護すると言う役割が果たせず、教皇権の権威なんぞどこかへ吹っ飛んでいた。1296年以降ローマ教皇ボニファティウスⅧ世とフランスカペー王朝のフィリップⅣ世(美王)は、教会領の課税を巡って激しく対立していた。1303年アナーニ滞在中の教皇を捕らえ退位させる。これがいわゆる「アナーニ事件」である。、1305年ボルドー大司教を教皇クレメンスⅤ世を擁立する。更に何と驚くべき事に1309年ローマ教皇庁をアヴィニョンへさらってしまう。ドイツはフランスに好きな様にやられていたのである。
諸侯は”待ってました”とばかりにハプスブルク家から王位を取り上げる。ルクセンブルク家のハインリッヒⅦ世がドイツ王に推挙される。1310年彼はフリードリッヒⅡ世以来約100年ぶりにローマで皇帝戴冠式を執り行い皇帝位に就く。1年前ボヘミア王国を手に入れており選帝侯も兼ねている。反ハプスブルクの旗頭でもあるハインリッヒⅦ世は、3つの州(シュヴァーツ、ウンターヴァルデン、ウーリ)を帝国直属としハプスブルク家からの独立を承認した。またハインリッヒⅦ世はフランスへの屈辱的状況の打開と皇帝戴冠を目指しイタリアに攻め入った。しかしながら皇帝戴冠式を行なおうにもヴァチカンはシチリア軍に占領されているし、肝心の教皇はアヴィニョンにいる。そこでハインリッヒⅦ世は”ラテラノ教会にて枢機卿に皇帝戴冠を受ける”という奇策を用いた。このまま順調に事が運べばルクセンブルク家は隆盛になるところであったが、1313年ハインリッヒⅦ世は僅か5年の在位で急死する。謀略による毒殺説があるが真相は定かではない。
ハインリッヒⅦ世が死去すると、ヴィッテルスバッハ家のバイエルン公ルードヴィッヒⅣ世とハプスブルク家のフリードリッヒ(美公)が名乗りを上げる。激しい争いの末ルードヴィッヒに凱歌があがる。ルードヴィッヒⅣ世は皇帝戴冠を望むがローマ教皇ヨハネス22世は拒否した。そこでルードヴィッヒⅣ世は”皇帝の権力は神から直接授けられたものである”と主張し、1328年1月ローマで「ローマ市民の推挙」を受ける形でローマ貴族コロンナ家から皇帝戴冠を受けた。更に教皇ヨハネス22世の廃位を宣告し、ニコラウスⅤ世を対立教皇とした。フランスの言いなりになっているローマ教皇庁に不満のある諸侯はこれを支持し、1338年フランクフルトの諸侯会議で「選帝侯により選出されたドイツ王は、教皇の承認無しに皇帝になる」と宣言した。
ところがローマ教皇は”腐っても鯛”、やはりローマ教皇である。”破門”という伝家の宝刀をちらつかせる。多少切れ味は鈍ったものの何のかんのと言っても効果は大きい。せっかくの対立教皇も全く役に立たずルードヴィッヒⅣ世は苦境に陥る。ローマ教皇庁との和解は成らず、それどころか教皇クレメンスⅥ世は「ルードヴィッヒⅣ世の破門と皇帝廃位」を宣告する。1346年選帝侯はルクセンブルク家のカールⅣ世をドイツ王として選出した。しかしながらルードヴィッヒⅣ世は対立王が現われても余裕でカールⅣ世を軽く叩き潰すつもりでいた。ところがここでもまた運命のいたずらか・・・1347年ルードヴィッヒⅣ世は事故で急死する。
これでカールⅣ世は単独王となり晴れて皇帝となる。この皇帝が『金印勅書』を発し、ドイツの、言い換えれば『神聖ローマ帝国』の行く末を定めることになる。このあたりの事情は次章で触れる。