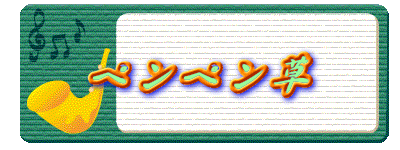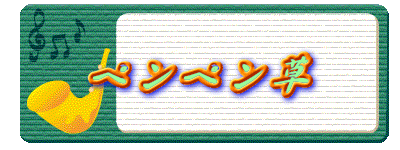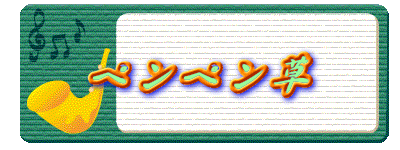第20段 * ハプスブルク家 その成り立ち Part1 * 始祖ルドルフⅠ世登場 *
ヨーロッパの歴史にハプスブルク家がはじめて登場したのは11世紀・・・と言ってもライン河上流のブルックという田舎の取るに足らない小さな貴族にすぎなかったが・・・。そんな小さな貴族がヨーロッパを代表する大帝国の君主にまで、そして1440年からハプスブルク帝国が崩壊する1918年まで「神聖ローマ帝国皇帝」の地位を維持することになった。(正確には「神聖ローマ帝国皇帝」は1806年まで、以降は「オーストリア帝国皇帝」を名乗る。)
ハプスブルク家は当初からウイーン(オーストリア)を拠点としていたのではない。私も以前は「ハプスブルク家」=「ウイーン」の図式しか思い浮かばなかった。スイスのバーゼルとチューリッヒを結ぶ線の西側、そこには鷹が飛び交う深い森があり居城があった。居城の名は「ハビヒツブルク(鷹の城)」、そこから家名が「ハプスブルク」と名づけられた。この地は河川交通の要所、ドイツとイタリアを結ぶ街道筋、つまり通商・交通上の重要な戦略拠点に位置している。地の利を生かしてハプスブルク家は一歩一歩勢力を蓄えていった。それほど目立つ活躍をしたわけでもないが、神聖ローマ帝国皇帝に忠誠を尽し地位を固めていったようだ。
それにしても『神聖ローマ帝国』とは何とも紛らわしい。何が「神聖」、「何がローマ帝国」なのか?古代のローマ帝国は395年に東西に分裂し、コンスタンチノーブル(現在のイスタンブール)を首都とする東ローマ帝国(ビザンツ帝国)とローマを首都とする西ローマ帝国になった。東ローマ帝国は強大な一つの王権の基に栄枯盛衰を繰り返しつつ、1453年の滅亡まで1000年以上継続した。一方西ローマ帝国は分裂後は東ローマ帝国に対して劣勢で、西ローマ皇帝は東ローマ帝国皇帝の承認を得なければならなかった。また375年に始まるゲルマン民族の大移動による諸部族の侵入で皇帝の力は弱まり、ゲルマン人の傭兵隊長の勢力が強くなった。西ローマ帝国は混乱を極め、476年傭兵隊長オドアケルは皇帝ロムルス・アウグストゥルスを廃位,ついに西ローマ帝国は滅亡した。その後800年フランク王国の国王カール大帝がローマ教皇レオⅢ世により皇帝戴冠、『西ローマ帝国』の名が再び甦ることになった。この『西ローマ帝国』は、962年「帝国」、1034年「ローマ帝国」、1157年「神聖帝国」、1254年「神聖ローマ帝国」、1512年「ドイツ国民の神聖ローマ帝国」と名を変えつつ、1806年にハプスブルク家のフランツⅡ世が”神聖ローマ帝国解散”を宣言するまで存続した。但しこの『西ローマ帝国』は古代の「西ローマ帝国」とは全く異質であることに注意しなければならない。(『神聖ローマ帝国』については第30段以降で触れることにする。)
そんなハプスブルク家に突然大きな転機が訪れる。まさに”瓢箪から駒”、”晴天の霹靂”というところか。1250年から1273年まで神聖ローマ帝国皇帝不在の「大空位時代」と呼ばれる。1250年は皇帝フリードリッヒⅡ世の死去、1273年はハプスブルク家のルドルフⅠ世が皇帝に即位した年にあたる。シュタウフェン家のフリードリッヒはローマ教皇インノセンティウスⅢ世の支持を得て皇帝となった。皇帝となったフリードリッヒⅡ世はあっさり教皇を裏切り、以降教皇と血みどろの争いを繰り返す。イタリア生まれイタリア育ちの皇帝は”古代ローマ帝国の栄光”復活を追い求めイタリア政策に奔走した。彼の壮大な構想実現の為に、諸侯と大幅な妥協を図った。それ故諸侯の権力は強大になり、皇帝とはほとんど名ばかりで皇帝の名でのドイツ統一は”夢のまた夢”となっていた。ドイツは無数の領邦国家が存在し、見事な?分裂国家になっていったのである。(以降ドイツは群雄割拠の状態が続き、1918年の帝国崩壊に至るまで”真の統一”はなされなかった。)
フリードリッヒⅡ世の死後シュタウフェン王朝は断絶し、約20年に亘り事実上皇帝位は空位となった。諸侯の権力が強大であり、必ずしも彼らの上に立つ絶対的な権力者を必要としなかったのである。有力諸侯が勝手に傀儡皇帝を擁立したが、誰一人としてローマ教皇から戴冠されなかった。当時神聖ローマ帝国はドイツ、オランダ、ベルギー、オーストリア、スイス、チェコ、イタリア北部、フランス東部など広大な領域を支配していた。そこの全体を統括するボスが不在では収拾がつかず崩壊してしまうはずが、そうはならないところがこの帝国の摩訶不思議。混乱の続く中ローマ教皇グレゴリウスⅩ世は1272年諸侯に対し、「新国王の速やかな選出」と「選出できない場合は教皇自ら新国王決定」を通告した。
神聖ローマ帝国の統治者がローマ皇帝、皇帝継承者がローマ王である。皇帝は選挙で選ばれていた・・・とは言っても現代の様な選挙とはまるで異なる。選挙で皇帝に推挙された者がローマにて教皇から戴冠され正式に皇帝となる。この時代皇帝選挙権は7人の選帝侯の特権となっていた。(この選帝侯、単なる皇帝選挙人ではない。選帝侯は1356年の金印勅書により様々な強大な特権を得る。)3人の大司教(マインツ、ケルン、トリア)と4人の君主(ボヘミア王、ザクセン候、ブランデンブルク辺境伯、プァルツ宮中伯)から成り、世襲制で1806年まで基本的には変わらなかった。選挙とは言っても立候補者がいて秘密投票で決めるのではない。選帝侯の意思、それも彼らの思惑のみで皇帝が決められた。そこには賄賂、闇取引が横行し、4人の君主のみならず3人の聖職者も欲の権化と化していた。
さて教皇グレゴリウスⅩ世に最後通牒を突きつけられ、さすがの横着な選帝侯も動かざるを得ない。当初の本命、有力候補は帝国最大の実力者ボヘミア王オットカルⅡ世・・・当時ボヘミアは群雄割拠の時代と言えどもその勢いは他を圧していた。誰もが認めていたのだからこの王が選ばれて当然か・・・と思うがそうではない。彼のこの類稀なる実力が選帝侯から疎んじられた。先ほども書いたが、選帝侯にとっては自分達の権力を維持する為にはそんな優れた人材は不要。そんな意味でハプスブルク家のルドルフは最適であった・・・はずだった。選帝侯から見れば、「ルドルフは真面目で忠実だが、財政もそれほど豊かではなく、またたとえ彼が死んで家系が途絶えてもどうと言うことはない。代わりはいくらでもいる」ちっぽけな存在にすぎなかった。ところがどっこい、天下人になったルドルフⅠ世はなかなかしたたかであった。彼は見かけによらず精力的で、頭脳明晰、機を見るに敏、忍耐強く、巧みな政治力、情に厚く人望もあった。とにもかくにもいろいろな思惑が交錯してハプスブルク家の始祖、『ルドルフⅠ世』が誕生した。
この時ルドルフは包囲していたバーゼルの総攻撃を翌日にひかえ興奮の極致にあった。そんなところに使者が到着、ルドルフに会議の結果を伝えたと言う。予期せぬ出来事が起きればそれは絶句する。総攻撃は中止、バーゼル司教と和議を結び急ぎ会議の場、フランクフルトへ取って返した。後で事情を知ったバーゼル司教は悔しさのあまり烈火の如く怒ったと言う。織田信長が本能寺の変で殺された時、豊臣秀吉が包囲していた高松城の毛利一族と和議を結び京都へ取って返した『大返し』と言ったところか。さすがである・・・スイスのちっぽけな伯爵がなんと帝国全体の王となった人の逸話としては相応しい。
さておもしろくないのは当初の本命、野心家のボヘミア王オットカルⅡ世・・・自分より格下と思っているルドルフに王位が渡ったのだから憤懣やる方がない。本来彼は国王への臣下の礼をとるべくアーヘンでの戴冠式、封土貸与の儀式に出席しなければならない。特に封土貸与の儀式は不愉快極まりない。例え形式的にせよ国王ルドルフⅠ世に前で膝まづき、ボヘミアの領地を拝領するなどと言うことは”屈辱”以外の何者でもない。3度に亘る国王の召喚勧告にも拘らずオットカルは拒絶、国王はオットカルを帝国追放処分にし追討することに決定。1276年オットカル追討軍はボヘミアに向かい出撃した。この様な場合何と言っても人望と大義名分が勝敗の帰趨を定める。明らかに国王ルドルフⅠ世に利がある。ウイーンの北東にあるマルヒフェルトでの激闘の末、皇帝軍に凱歌が上がりオットカルは戦場の露と消えた。天下を取った豊臣秀吉に抵抗し敢え無く散った柴田勝家、浅井長政、朝倉敏影と同じようなものだ。
この勝利でハプスブルク家は一躍ヨーロッパにおける地位を著しく向上させた。スイスの一小貴族とあなどりお情けで国王の地位を恵んだつもりが、勇将オットカルを撃破しその名を天下に轟かせることになったのだから。この勝利でハプスブルク家はオットカルが所有していたオーストリア、シュタイアーマルク州、ケルテルン州などを手に入れた。この時ハプスブルク家とオーストリアとの結びつきが生まれ、後にオーストリアへ活動の拠点を移すことのなった。一方もともとのスイスの所領はルドルフⅠ世の国王就任時の諸侯との約束の履行(所領の割譲)や帝国自由都市の反抗で手放さざるを得ない状況に追い込まれた。彼は歴代の皇帝がイタリア掌握に懸命になっていたのに対し、自分の足場を固めることに専念した。それが故に彼はローマへ赴くことはなく、教皇から戴冠を受けることはなかった。即ち皇帝とはならなかった。
選帝侯ら諸侯は思わぬ見込み違いにはかなり慌てたようで、ルドルフⅠ世の死後国王を他家から選出した。その後150年もの「選帝侯の時代」には、国王の位はまるで持ち回り、将棋の駒の様にめまぐるしくあちらこちらと動いた。1440年ハプスブルク家のフリードリッヒⅢ世が皇帝となり、以降1918年まで478年間に亘り皇位を継承し続けたのは何ともすごいことだ。
もともと取るに足らぬさほど恵まれた家系ではなかったハプスブルク家がこれほど長期間皇帝位を維持できたのだろうか?強力な権力を有した選帝侯を押さえ込むことができたのだろうか?それはハプスブルク家の独特の結婚戦略によるものである。次章ではそこに焦点を当てる。