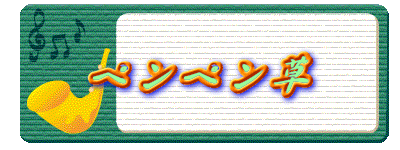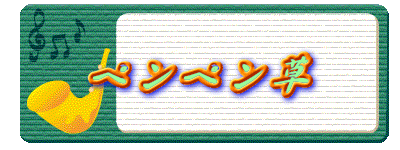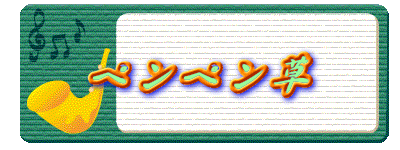第31段 * 神聖ローマ帝国 その成り立ち Part2 * ドイツ王国の誕生 *
911年カロリング家の断絶を受けて、フランケン公コンラートが東フランク国王に”選挙”で選ばれた。選挙とは言っても現在の様な選挙とは異なる。古来ゲルマン王家では”世襲選挙王制”の形式をとっていた。国王には誰でもなれたわけではなく、基本的にはあくまでも前国王の縁者が後継者の資格を有している。更に前国王は後継者を指名する権利を持っている。ここで言う選挙とは形式的なもので、”真に国王に相応しい国王が選ばれた”ことを証明する為の儀式と考えて良い。但し例外があり、前国王の血筋が断絶した場合、あるいは前国王の縁者が国王には相応しくない極悪非道な人物の場合などは選挙の意味合いが一変する。
コンラートⅠ世が選ばれた時はまさにこの例外に該当する。カロリング家のカールⅠ世に完璧に押さえ込まれていた大貴族・・・後に(ドイツ)諸侯と呼ばれる・・・にとっては、王権に制限を加えて権限拡大の絶好のチャンスを得たのである。カールⅠ世の死後大貴族は、国王の権威をないがしろにして各々の権勢拡大を図っていた。強大な国王なんて彼らにとっては迷惑千万なのである。そんな状況下で選ばれたコンラートⅠ世は終世苦難の道を歩む。対外的にはマジャール人や西フランク王国の血を引くシャルルⅢ世の侵攻に苦しめられる。東フランク王国内では強大な権勢を持つバイエルン公やザクセン公などが容易に国王には従わない。ザクセンが東フランク王国から分離独立を断念させる為、コンラートⅠ世は実弟ではなくザクセン公ハインリッヒを後継者に指名した。コンラートⅠ世は憤懣やる方ないままこの世を去った。ここにフランク人とは全く無関係の「ザクセン王朝」が誕生した。これで東フランクはフランク族の支配から離れ、ゲルマン民族の国家がおぼろげながら見えてきた。見方を変えると『ドイツ王国』の誕生とも看做せる。
ここで後に(ドイツ)諸侯と呼ばれる大貴族について触れる。大貴族とはフランク王国内において公爵位と宮中伯、辺境伯などの伯爵位を授けられた者を指す。つまり高級官僚、いわば国家公務員の高級幹部と言ったところである。本来は国王が任免権を持ち世襲などあるはずもない。しかしながらいつのまにか地方に派遣された公爵、伯爵が土着勢力となり、軍事、民政などに様々な権限を持ち公爵位、伯爵位の被任免権を独占する様になる。国王から委託された地方統治を世襲のものとし、国王の権威をないがしろにする大きな抵抗勢力的存在になっていった。歴代の国王は公爵、伯爵、後には司教、ローマ教皇庁らとその権限を巡ってせめぎあうことになる。
919年ハインリッヒⅠ世は初代「ドイツ王」に就いた。国内におけるバイエルン、シュヴァーベンとの対立はいくつかの自主的特権を与えて切り抜けた。対外的にはスラヴ族、マジャール人、デーン人の侵入を退けザクセン領を防衛した。西フランクのシャルルⅢ世との外交交渉でロートリンゲンの奪還に成功した。ハインリッヒⅠ世の治世は軍事・外交面では一定の成果をあげたが、内政では各部族の分立指向の意識が強く課題を残した。
936年ハインリッヒⅠ世がこの世を去ると、次男オットー(大帝)がドイツ王となる。当時ドイツ王国は相変わらず各部族の分立指向が強く、統一国家としての体裁をなしてはいない。当時カール大帝の遺産とも言える教会組織が存在していた。この”教会”はローマ教皇の支配にある教会とは違う。異教の時代にゲルマン民族は多くの私有寺院を建設するが、キリスト教化されるとそれらは私有教会となる。この私有教会領はローマ教会支配下の司教領とは異なり、あくまでも”個人の所有”に属するものである。ローマ教会も手を出すことができない。オットーⅠ世はこれらの教会領に関税権、貨幣鋳造権などの特権を与え保護した。ドイツ国内随所に散らばる教会領を駆使して、王権に抵抗する各部族の分断を狙った。教会領は司教が治めるが、司教は聖職者独身制度の為自らの血筋に継がせることができない。更に国内のローマ教会支配下の司教領にも、オットーⅠ世の権力を行使し自らの支配下においた。国内での司教「叙任権」をオットーⅠ世が掌中にしたのである。これがいわゆる『帝国教会政策』である。
本来であれば教皇権への侵害であるから、ローマ教皇はオットーⅠ世のこのようなやり口に対抗しなければならない。しかるに当時ローマ教皇領は中世イタリア王国のベレンガリオⅡ世に繰り返し侵略されていた。止むを得ず教皇ヨハネスⅩⅡ世はドイツに支援要請する。961年オットーⅠ世はイタリア遠征にてベレンガリオⅡ世を破る。翌962年2月オットーⅠ世はローマで教皇より戴冠され皇帝となった。但しカール大帝の場合とは異なり、教皇にしてやられることはなかった。教皇は皇帝に従うことを誓う。そして教皇に「オットーの特許状」・・・ローマ教皇領の保証、教皇選挙への助力の約定・・・を与える。”皇帝の教皇選挙への助力”とは言い換えれば”教皇選任に際しては皇帝の承認が必要”と言うことである。よくもこのような屈辱的な条件を教皇が飲んだものだ。
やはりこれには裏がある。素直に従う様な教皇ではない。すぐさま教皇はかつての仇敵ベレンガリオⅡ世、ビザンツ帝国、マジャール人と手を結び”反オットー戦線”を築こうとする。室町幕府15代将軍足利義昭が織田信長の援助を受けながら、後に裏切り”反信長”の激を全国に飛ばしたのと良く似ている。いつの時代、どこにも権力闘争の陰には同じようなあるものと妙なところで感心する。しかしオットーⅠ世は素早く教皇の動きを察知し反撃に出る。ヨハネスⅩⅡ世の廃位と新教皇レオⅧ世の選任を決め、更にイタリア国王ベレンガリオⅡ世を退位させた。これでオットーⅠ世はドイツ王とイタリア王を兼ねることになったのである。彼の治世は973年まで続く。
これで『神聖ローマ帝国』の誕生とはなったわけではない。オットーⅠ世は「皇帝アウグストゥス」と称した。息子オットーⅡ世は当初父に同じ、976年以降は「ローマ人達の皇帝アウグストゥス」と称する。オットーⅡ世の息子オットーⅢ世、ザクセン家最後の皇帝ハンリッヒⅡ世も「ローマ人達の皇帝アウグストゥス」と称した。ザクセン王朝の時代、皇帝は一度も「ローマ帝国皇帝」を名乗ることはなかった。たしかにドイツ、イタリアを支配してはいたが、かつて古代ローマ帝国が支配していた広大な領域とは比べ物にならない。おそらくこれでは「ローマ帝国皇帝」を名乗るのは気が引けたのだろう。それでザクセン王朝の帝国には呼称すべき名前が無い。
オットーⅠ世が始めた『帝国教会政策』は帝国全域を統治するのに大きな役割を果たした。しかしながらこれが機能するのは教会組織が”皇帝の掌中の球”であることが前提となる。つまり「皇帝の叙任権」、「教皇選任への承認権」が皇帝の意のままに扱える必要がある。裏返せばローマ教会が「そんなこと知るか!」と牙を剥き出せば”砂上の楼閣”の如く崩れ去る。ローマ教皇が”飼い猫”の様に皇帝にいつも媚びへつらっているわけがない。教皇は絶えず隙あらばと権某術策を張り巡らし皇帝に抵抗し続けた。皇帝と教皇の確執はヨーロッパの歴史のいたる所に現われてくる。
当時北イタリアは貨幣経済が進み潤った都市が勢力を拡大し『帝国』と衝突を繰り返す。皇帝は反乱鎮圧の為都度イタリア遠征を行なった。膨大な戦費が必要となりドイツ諸侯からの支援としたが、諸侯が「はい、わかりました」と黙って支援するはずがない。皇帝は代償として、領地購入権、「相互相続契約」締結権などの様々な特権を諸侯に付与した。これではますます諸侯の権勢が拡大し、相対的に皇帝の権威が弱くなってくる。だから中世以降のドイツには”真の”統一国家が成立しなかったのだと思う。これを見ていると、室町幕府の将軍と守護大名の関係が脳裏に浮かんでくる。
1024年ザクセン家が断絶し、フランケン公コンラートⅡ世がドイツ王に選出され『ザリエリ王朝』が誕生する。むろんイタリア王も兼ね皇帝位に就く。またブルゴーニュ王国の断絶を機にブルゴーニュを掌中に収めた。これでドイツ、イタリア、ブルゴーニュから構成される帝国の支配領域とした。カール大帝時代の復活「西ローマ帝国」にははるかに及ばないが、それでも「ローマ帝国」を称してもおかしくない領土を有している。それでコンラートⅡ世は4通の皇帝公文書の中で自らの帝国を『ローマ帝国』と名付けた。しかしながらまだ”神聖”の2文字はどこにもない。
コンラートⅡ世はザクセン家の「帝国教会政策」を更に強化した。この頃のローマ教皇やイタリアの反皇帝勢力の勢いがない。有力な司教領も帝国直轄、つまり教皇から奪い取ったのである。と言うことは心おこなく内政に専念できる。王料地・・・皇帝の直轄領域・・・の拡大を図り、皇帝直属の家臣(ミニテリアーレス)にその管理を委託する。ミニテリアーレスを随所に配置し、王領地周辺の諸侯への牽制役とした。皇帝は在位中にミニテリアーレスにも諸侯に変わらぬ権利を与え力をつけてくるが、その影響が出てくるのはまだ先の話。これで王権は強化された。
1039年コンラートⅡ世がこの世を去り、息子ハインリッヒⅢ世がドイツ王となる。後のハインリッヒⅣ世の時代に有名な「カノッサの屈辱」が起きる。そのあたりについては次章で触れることにする。