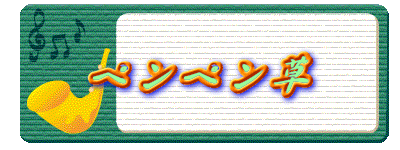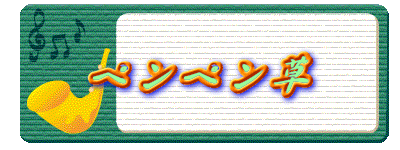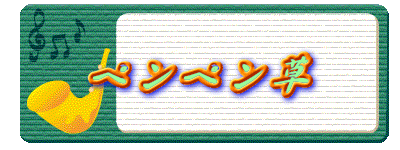第38段 * 神聖ローマ帝国 その成り立ち Part8 * 30年戦争とウエストファリア条約 *
1619年”反宗教改革”の急先鋒フェルディナンドⅡ世が皇帝位に就く。彼が皇帝位に就くだいぶ前からカトリック諸侯とプロテスタント諸侯の世俗的利害対立は激化していた。ついに『神聖ローマ帝国』内に2つの軍事同盟・・・バイエルン公をリーダーとする”旧教徒連盟(リーグ)”と、プファルツ選帝侯をリーダーとする”新教徒連合(ユニオン)”・・・が結成され抜き差しならぬ状況にある。こんな状況下でプロテスタント側から”危険人物”と見做されているフェルディナンドⅡ世が表舞台に現われたのである。
1618年ベーメン王国のプラハ城での「突き落とし事件」・・・ボヘミアの新教徒がマティウス帝の顧問を王宮の窓から突き落とした・・・が引き金となり、いわゆるドイツ30年戦争が勃発した。直接参戦したのはドイツ、スペイン、デンマーク、スウェーデン、フランスであるが,スペインと独立戦争を戦っていたオランダ、それとスペインと対立していたイギリスもこの戦争に関わった。突き詰めれば基本的な対立の構図は、フランスvsハプスブルク家の図式である。
第1ラウンドは1618年から1624年にかけてのボヘミア・プファルツ戦争である。皇帝フェルディナンドⅡ世の相手、ボヘミアを奪ったユニオンのトッププファルツ選帝侯フリードリッヒⅤ世を打ちのめす。プロテスタント諸侯の足並みが揃わずそこを突かれた。皇帝はフリードリッヒから選帝侯位を取り上げ、リーグのトップバイエルン公マキシミリアンⅠ世に与える。これは明らかに『金印勅書』違反であり、諸侯から怒りの声が上がるが皇帝は無視する。
第2ラウンドは1629年にかけてのデンマーク戦争である。ここでも皇帝は新しく貴族に任じた傭兵隊長ヴァレンシュタイン伯アルブレヒトを皇帝軍総司令官に任命し、彼の活躍でデンマークにも圧勝する。皇帝はデンマークと「リューベックの和約」を結びドイツから追い出した。
1629年3月皇帝は”皇帝権力の強化”と”プロテスタントの排除と再カトリック化”を目的とした『回復令』を発した。その内容とは・・・”カルヴィン派を宗教和平から除く。プロテスタントに没収された教会領はカトリックに返す。バルト海艦隊の建造の即時着手。”など・・・。更に皇帝は「ハプスブルク大政策」を振りかざす。その内容とは・・・”諸侯は皇帝の許可なく武力を持ち同盟を結ぶのを禁止する。皇帝位はハプスブルク家の世襲とする。”など・・・。さすがにこれにはバイエルン公はじめとする諸侯は強く抵抗する。これを認めれば”ハプスブルク家絶対主義”を確立させることになる。皇帝もカトリック諸侯に逆らわれては潰れてしまう。1630年8月ヴァレンシュタイン伯は皇帝軍総司令官を罷免される。
第3ラウンドは1635年にかけてのスウェーデン戦争である。フランスから援助を受けたスウェーデン王グスタフ・アドルフはドイツに戦いを仕掛ける。初期はスウェーデンが優勢であり、劣勢に陥った皇帝は背に腹を代えられずヴァレンシュタイン伯を好条件を提示し召還する。1632年11月ライプチヒ近郊リュッツェンで両軍は対峙した。スウェーデン軍優勢であったが、リュッツェンの戦いでスウェーデン王は戦死してしまう。一方1634年2月ヴァレンシュタイン伯は不穏な動きありとして、皇帝の指示で暗殺されてしまう。最終的には皇帝の甥フェルディナント3世の活躍で皇帝軍が逆転勝利を収める。1635年5月皇帝が『回復令』を撤回し、皇帝側に有利な条件でプラハ和約が結ばれる。
ここで終結すれば皇帝の大勝利となった・・・はずであるがそうはならなかった。ここで1635年5月ハプスブルク家の宿敵フランスが、”プロテスタントの黒幕”から一転してスウェーデン、オランダと同盟を結び参戦してきた。第4ラウンドはプロテスタントvsカトリックの対立の構図がどこかへ吹っ飛び、フランスvsドイツの因縁の対決の様相を帯びてきた。これで戦局は一変、プロテスタント側に有利に大きく傾いた。1637年皇帝フェルディナンドⅡ世がこの世を去り、嫡男フェルディナンドⅢ世が皇帝となる。1643年5月ロクロウでスペイン軍がフランス軍に大敗した為、スペイン・ハプスブルク家から支援を受けることの出来なくなった皇帝軍側はしだいに劣勢になっていく。フェルディナンドⅢ世はフランスへの敵愾心を剥き出しにして奮闘するも、長期戦で膨大な死者と国土の荒廃でさすがに厭戦気分が満ち溢れ和平を求める声が大きくなってきた。
1648年1月からヴレストファーレン公国内に点在するミュンスター、オスナブリュックなどの司教領で開催された。ローマ教皇、ヴェネツィアやポルトガルの様に戦争に無関係な国までも加わり,参加国66カ国にも及ぶヨーロッパ史上最大の国際会議である。同年10月神聖ローマ皇帝、ドイツ諸侯及び帝国都市、フランス、スウェーデンとの間で、ウエストファリア(ドイツ語でヴレストファーレン)条約が調印された。この結果最も得をしたのはフランス、次いでスウェーデン、オランダ、逆に打撃を受けたのはドイツ、スペインと言うことになる。この条約の主な取り決めは以下の通り。
・アウグスブルクの和議の原則の再確認、及びカルヴィン派への適用拡大。
・皇帝の立法権、条約締結権は帝国議会に拘束される。
・諸侯と帝国都市は皇帝と帝国を敵としない限り主権を有する。
・スウェーデンはドイツ北部の複数の諸侯領を獲得。・・・実質(ドイツ)諸侯となる。
・フランスはメッツなどの3司教領とアルザス地方を獲得。・・・実質(ドイツ)諸侯となる。
・オランダ、スイスの神聖ローマ帝国からの分離・独立を正式に承認。
など・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
諸侯と帝国都市は(皇帝と帝国を敵としない限り)主権を持つことになった。これにより選帝侯の皇帝選挙権を除く全ての特権がなくなり、全ての諸侯が同権を有する、つまり同列になったのである。諸侯間、諸侯と外国と同盟を結ぶことができる。”同盟権がある”と言うことは裏返せば”交戦権”があると言うことでもある。大きくても小さくてもそんなことは無関係、約300もの独立国(領邦国家)が乱立することなった。ドイツの統一国家誕生が大幅に遅れる事が決定的になる。これは『神聖ローマ帝国』の弱体化、言い換えれば『神聖ローマ帝国』が完全な”死に体”である事をを意味している。これがウエストファリア条約が「神聖ローマ帝国の死亡診断書」と言われる所以である。ヨーロッパから”中世的世界帝国理念”が消えたのである。
この頃にはローマ教皇のかつての威光もすっかり色褪せていた。あれほど世俗世界、世俗権力に色気を出し、『神聖ローマ帝国』と皇帝に対して”教皇の権威”を誇示していたのが嘘の様だ。かつて皇帝と教皇の間で”叙任権”を巡り紛争を繰り返してきたのだが・・・。カールⅣ世の時代に”ローマ教皇の承認不要”を帝国法として定めた。更にマキシミリアンⅠ世の時代には教皇の戴冠式さえ無くなっている。このウエストファリアの会議には”お呼びでない招かざる客”としてローマ教皇が出席し大きな顔をして口出しをしたので顰蹙をかっている。もはや世俗権力に対してほとんど影響力は失せているのに勘違いしていたのだろうか?それとも存在感を示す為に見栄を張っていたのだろうか?いずれにせよローマ教皇庁は世俗権力からますます遠ざかる。”宗教者本来の姿”に、即ち”宗教者としての原点”に回帰して行く道を歩むことになったと言えるのではないだろうか?
ウェストファリア条約によって定められたドイツ国家体制は1806年の帝国解散まで維持された。しかしながらハプスブルク家の絶対主義による皇帝権の回復の夢は断たれる。また『神聖ローマ帝国』は有名無実となる。一方、フランスはヨーロッパ最大の強国にのし上がり、17世紀後半にはブルボン王朝ルイⅩⅣ世の時に絶頂期を迎える。このあたりの事情は次章で触れることにする。